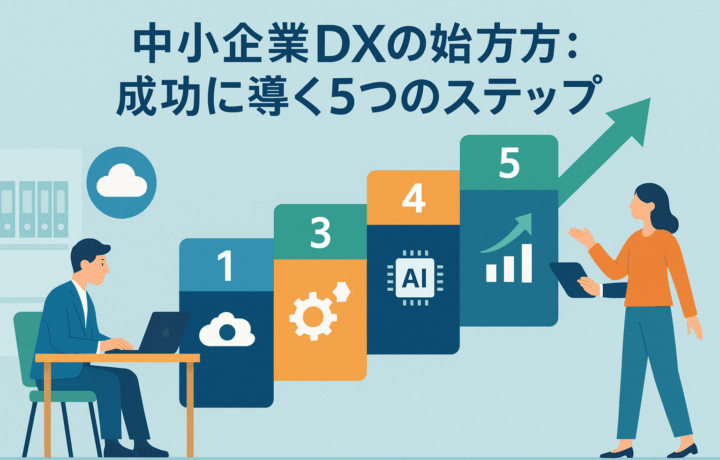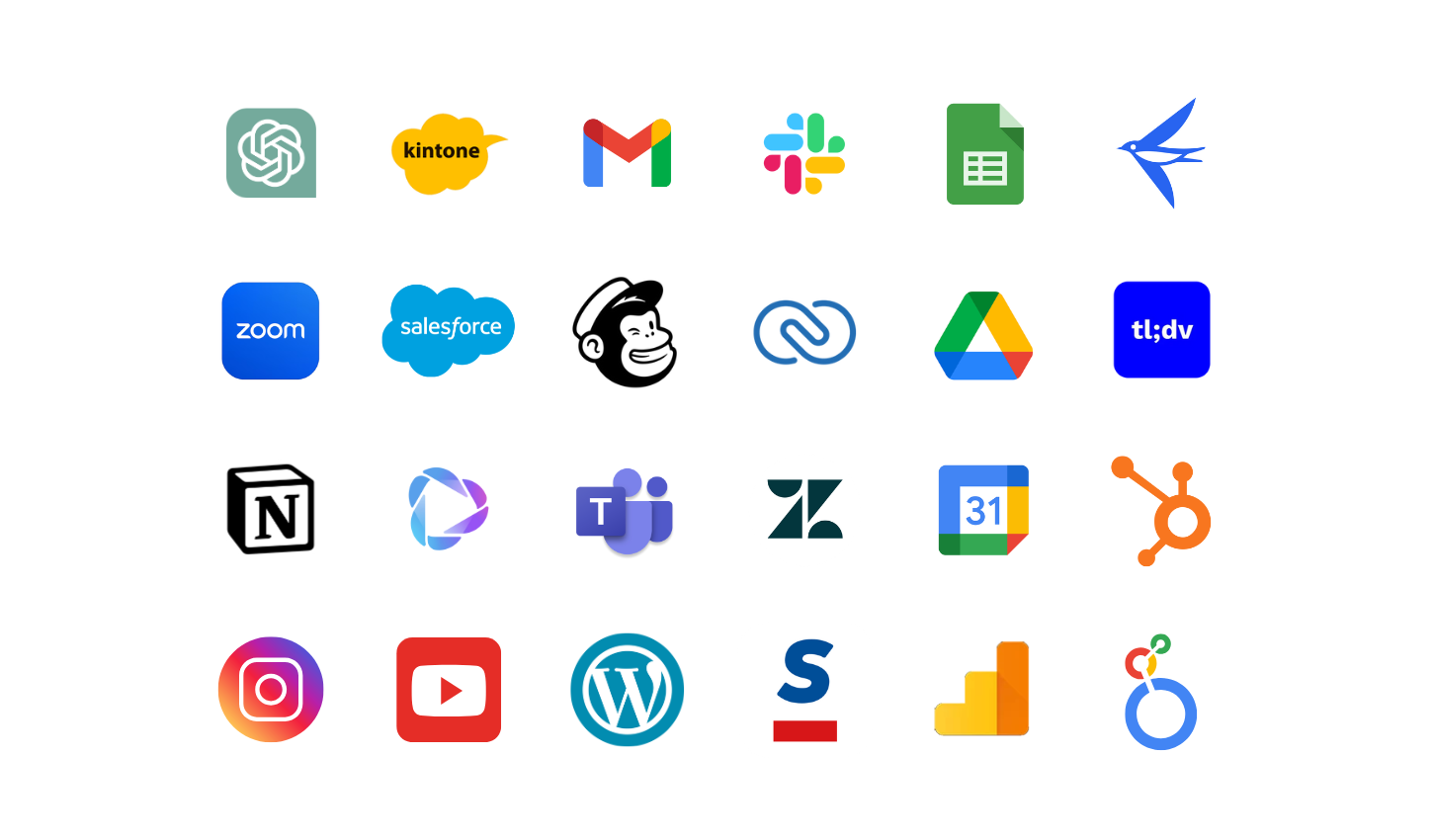デジタルトランスフォーメーション(DX)は企業競争力を高める鍵ですが、「何から始めればいいのかわからない」「今のままで十分ではないか」と着手をためらう中小企業も少なくありません。
特にマーケティング部門や業務改善担当者にとっては、DX推進の必要性を感じつつも具体策が見えず、プロジェクトが進まないケースが多いでしょう。
また「DXは大企業がするもの」という先入観から自社では無理だと考えてしまう企業もあります。
しかし実際には、人手不足の解消や業務効率化、顧客満足度向上など中小企業こそDX推進で得られるメリットが大きいと言われています。
現状、日本の中小企業のDXへの理解度は約5割と高まりつつあるものの、具体的にDXに取り組めている企業は3割程度にとどまっています。
多くの企業が請求書の電子化やセキュリティ対策といった部分的なデジタル化には着手している一方で、AI・IoTの活用やRPAによる業務自動化まで踏み込めている企業はごくわずかです。
高度なDX施策が進まない背景には、「導入が難しい」「コストがかかる」「使い方が分からない」「人材が足りない」といった理由があり、多くの中小企業がDX推進に課題を抱えているのが実情です。
そこで本記事では、中小企業がDXを成功させるための5つのステップを、よくある課題とその解決策、具体的な事例や活用イメージと共に解説します。
自社のマーケティング業務や日々の業務改善にすぐ役立てられる内容ですので、DX推進に悩む担当者の方はぜひ参考にしてください。
ステップ1:現状の業務課題を洗い出す
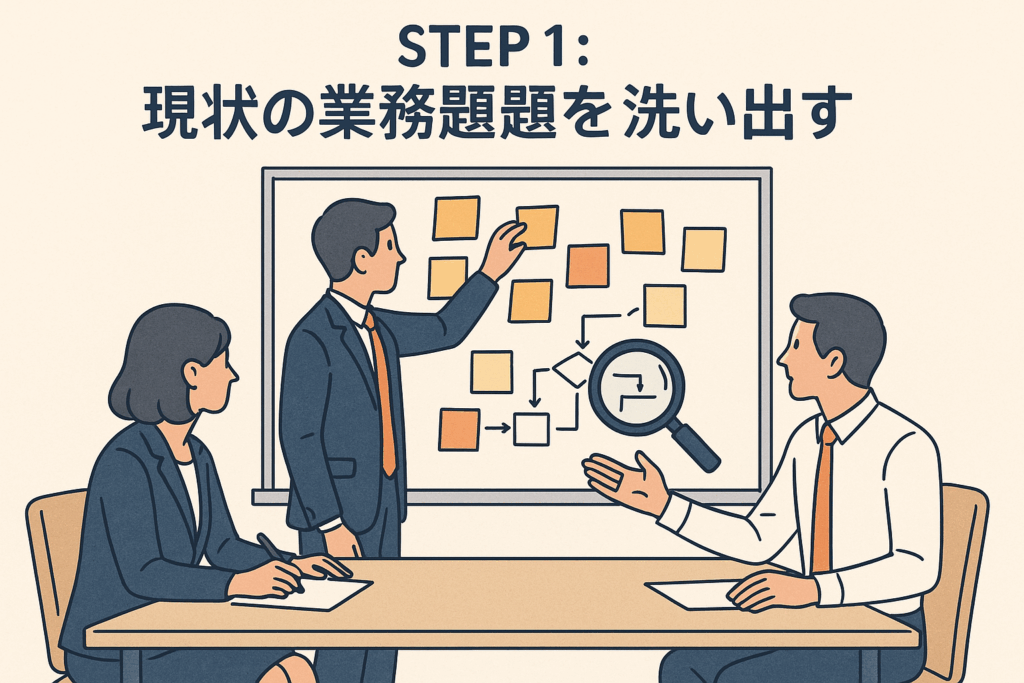
まず最初のステップは、自社の業務プロセスを見直し現状の課題を明確化することです。
どの部署であれ、闇雲にデジタルツールを導入する前に「何を改善すべきか」を把握することがDX成功の土台となります。
よくある課題: 自社の非効率な業務やボトルネックが把握できていないことです。
例えばマーケティング部門では「問い合わせ対応に時間がかかり見込み客へのフォローが遅れている」「Excelでの手作業集計に工数を取られて分析や戦略立案に時間を割けない」といった問題が潜在しているかもしれません。
しかし日々の業務に追われていると、そうしたムダや機会損失に気づきにくいものです。
解決策: 業務の棚卸し(洗い出し)を行いましょう。
関係者を集め、現行の業務フローや手順を一つひとつ書き出してみてください。以下の観点でチェックすると課題が見えやすくなります。
- 時間がかかりすぎている業務はないか?(例:データ入力やレポート作成に過剰な時間を要していないか)
- 生産性を阻害している無駄な手順は何か?(例:二重入力や紙書類の受け渡しなど冗長なプロセス)
- デジタル化で効率化できそうな作業はあるか?(例:定型的・繰り返し作業、ヒューマンエラーが多い作業)
- 顧客体験の向上につながる改善点はないか?(例:顧客からの問い合わせ対応スピードやサービス提供プロセスの改善点)
現場の担当者へのヒアリングや業務ログの分析も有効です。
たとえばメール対応に追われて残業続きになっている、といった声があれば「問い合わせ対応の自動化」が一つのDX候補課題として浮かび上がります。
マーケティング部門であれば顧客データ管理の不備や、複数チャネルの情報が統合されていない点が課題かもしれません。このように現状の課題をリストアップできれば、DXによって解決すべき優先課題が明確になります。
事例: ある製造業の中小企業では、全社的に業務を洗い出した結果、「受発注データの手入力」「在庫情報の紙帳票管理」が大きな非効率箇所だと判明しました。
そこでこれらをデジタル化・自動化するDXプロジェクトを立ち上げ、結果として在庫管理や生産計画の精度向上につながっています。
まずは自社の現状を把握することで、DXの出発点となる解決すべき課題を見極めることが重要です。
ステップ2:DXの目的とビジョンを設定する
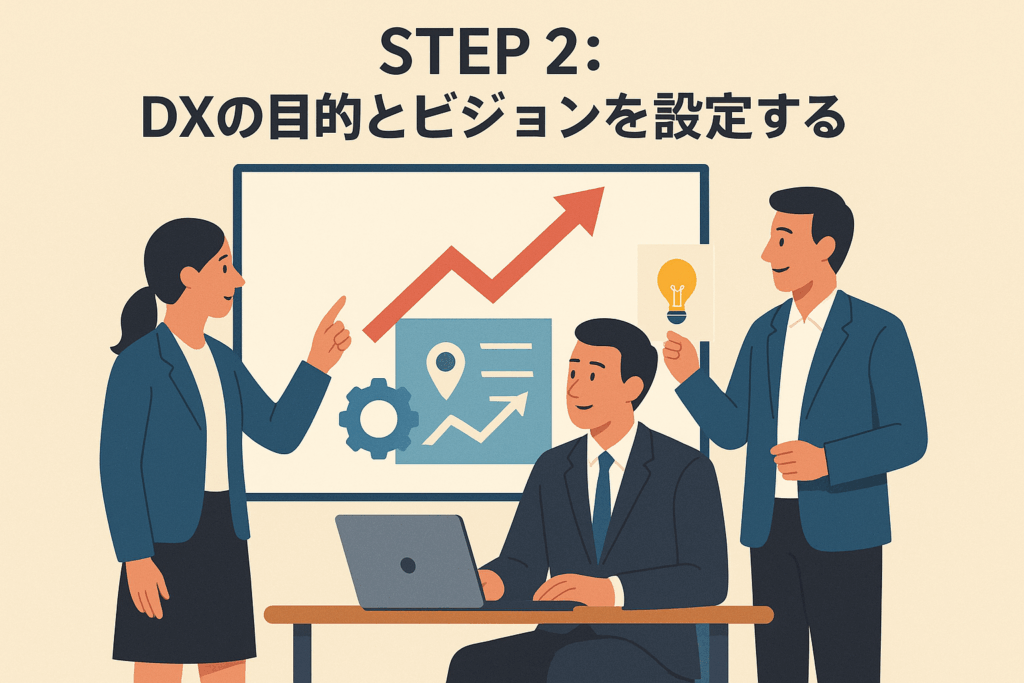
続いて、明らかになった課題を踏まえてDX推進の目的やビジョンを明確化します。
ここでは「DXを通じて何を達成したいのか」を経営目線で定義し、社内で共有することがポイントです。
よくある課題: 目的が不明瞭なまま「とりあえずITツールを入れてみよう」と進めてしまい、結局現場に定着しないケースが少なくありません。
また経営陣の理解やコミットメントが不足していると、現場任せになってプロジェクトが頓挫しがちです。
特に中小企業では経営者の意識とリーダーシップがDX成功の鍵を握りますが、担当者だけが意気込んでも上層部の賛同が得られず停滞する、といった事態は避けたいところです。
解決策: DX導入の目的を具体的な目標として設定し、経営層と現場で共有することが重要です。
まず経営者や上長と協力し、会社のビジョンに沿ったDXのゴールを定めましょう。
目標は可能な限り定量化し、測定可能なKPIで表現します(例:「1年でマーケティングリード対応のスピードを2倍に向上」「3年で営業一人当たり年間売上を1.5倍にする」など)。
こうした具体的な目標設定によりDX施策の方向性がぶれず、成果も評価しやすくなります。
次に、その目的・目標を社内でしっかり共有・周知しましょう。
経営トップ自らがDX推進の意義を全社員に説明し、推進チームを発足して定期的に進捗確認を行うなど、リーダーシップを発揮することが理想です。現場の担当者に対しても、DXによって得られるメリット(業務負荷の軽減や生産性向上、働き方の改善など)を具体的に伝え、協力を得ます。
例えばマーケティングDXの場合、「ツール導入で手作業が減れば、その分戦略立案やクリエイティブに集中できる」という将来像を示すと現場のモチベーションも上がるでしょう。
事例: とある小売業の会社では、「オンライン経由の売上比率を2年で50%に引き上げる」というDXビジョンを掲げ、経営陣が主導してECサイト構築やSNSマーケティングに取り組みました。
その結果、新規顧客の獲得が順調に進み売上を大幅増加させています。このように経営者が明確な目標を示し陣頭指揮を執ることで、社員も一丸となってDXを推進できるのです。
ステップ3:DX推進のための人材とリソースを確保する

目的が定まったら、DXプロジェクトを推進するための人材と必要リソースの準備に取りかかります。
計画を実行に移すには、専門知識を持った人材や十分な時間・予算の確保が欠かせません。
よくある課題: 中小企業ではDXを担う人材が社内にいない、または人的リソース自体が不足しているという問題がよくあります。
IT部門がない企業や、マーケティング担当者が兼務でDX推進を任されているケースでは、「ノウハウがなく何をどう進めれば良いか分からない」という状況に陥りがちです。
またDXのための予算不足も大きなハードルです。限られた人員・資金の中で通常業務と並行してDXを進めるのは容易ではありません。
解決策: DX推進チームや担当者を明確に定め、必要に応じて外部の力も活用することが効果的です。
まず社内でDXに関心とスキルのあるメンバーを募り、小さくても良いのでプロジェクトチームを組成します。
マーケティング部門発のDXなら、マーケ担当者に加えて情報システムに明るい社員や現場のキーマンを巻き込むと良いでしょう。
社内に適任者がいない場合は新たに人材を採用したり、外部の専門家に協力を仰ぐことも検討してください。
近年はDX支援を専門とするコンサルタント会社やITベンダーも増えており、アウトソーシングの活用は有力な選択肢です。
DX化の最初におすすめなのが、弊社のオートラクボです。

専門知見を持つプロ人材のサポートを得れば、自社にノウハウがなくともDXをスムーズに進められるでしょう。
また、人材育成の視点も重要です。中長期的には現社員のデジタルスキル底上げを図り、自社でDXを推進できる体制を作ることが望ましいです。社内研修や勉強会の開催、オンライン講座の受講支援などでマーケティングDXに必要な知識(例えばデータ分析やマーケティングオートメーションの使い方等)を学ぶ機会を提供しましょう。
加えて、経営層も含め組織全体でDXへの意識改革を行うことが大切です。
DX推進は現場担当者だけの取り組みではなく、全社的なプロジェクトであるとの認識を浸透させます。
予算確保の工夫: 資金面の課題には、公的支援制度の活用が有効です。
現在、日本政府や自治体は中小企業のDX推進を後押しする補助金・助成金制度を多数用意しています。
例えばIT導入補助金やものづくり補助金、DX投資促進のための税制優遇など、条件を満たせばDX関連の投資に対して補助金交付や税控除が受けられます。
マーケティングツール導入や業務システム開発にも使える制度があるので、情報収集をしてぜひ活用してください。限られた予算でもこれら支援策を使えばDXの第一歩を踏み出しやすくなるでしょう。
事例: DX人材がいないある企業では、思い切って外部のDXコンサルタントにプロジェクトマネージャーとして参画してもらい、社内チームと二人三脚で改革を進めました。
その結果、わずか半年で複数の業務を自動化し、社員にもノウハウが蓄積され始めています。また別の中小企業では、社員のITリテラシー向上のためeラーニング研修を導入し、若手を「デジタル推進リーダー」に育成して現場を牽引させています。自社の状況に合わせ、人と資源の面からDXを推進できる下地を整えましょう。
ステップ4:解決策に適したデジタルツールを選定・導入する
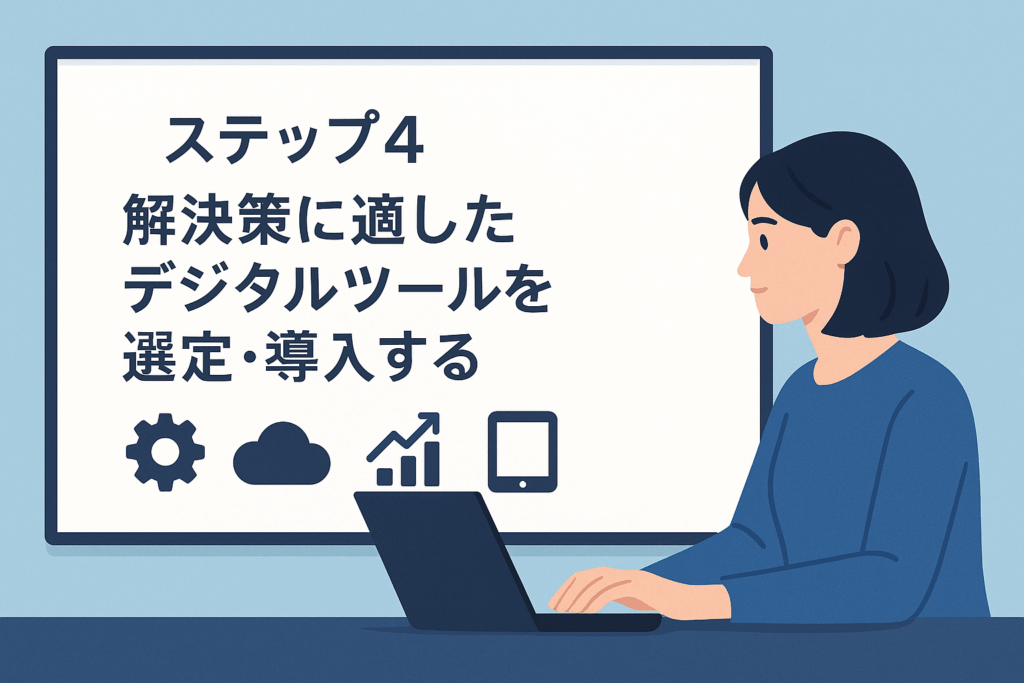
準備が整ったら、いよいよ具体的なデジタルツールやソリューションの選定・導入に移ります。ステップ1で洗い出した課題を解決する手段として、どのようなITツールを使うかを検討しましょう。
よくある課題: ツール選びで陥りがちなのは、「流行っているから」「他社も導入しているから」という理由で自社の課題に合わないシステムを入れてしまうことです。
これでは期待した効果が得られず、「DXは失敗だった」となりかねません。また、多数のクラウドサービスやソフトウェアが乱立する中で「どれを選べばいいのか分からない」と悩むケースも多いでしょう。
さらに、中小企業では予算やITインフラの制約が大企業以上に厳しく、高価なシステムや大掛かりな開発プロジェクトは現実的でないこともあります。
解決策: 自社の課題解決に直結するツールを慎重に選ぶことが肝要です。
基本はステップ1で特定した優先課題ごとに、「その課題を最も効率的に解消できる手段は何か?」を軸に検討します。
例えばマーケティング部門のDXで「見込み客管理に時間がかかっている」という課題なら、顧客関係管理(CRM)システムやマーケティングオートメーション(MA)ツールの導入が考えられます。
また「部門間でデータが共有されておらず意思決定に時間がかかる」という課題には、社内情報を一元化するグループウェアやデータ分析基盤の整備が解決策となるでしょう。
ツール選定の際は次のポイントをチェックしてください:
- 自社課題の解決に直結する機能を備えているか(課題との適合性が最優先)
- 操作性が高く現場で使いやすいか(難しすぎるツールは定着しない)
- 導入・運用コストは適切か(期待効果に見合った費用か、隠れコストはないか)
- 既存システムや他ツールとの連携は容易か(将来的な拡張性やデータ連携のしやすさ)
- セキュリティやサポート体制は十分か(安心して長く使えるサービスか)
特に中小企業の場合は初期投資を抑えられるクラウドサービスの活用が効果的です。
クラウド型のツールであれば自社サーバーを用意する必要もなく、月額課金で必要な機能だけ使えるためコスト負担を平準化できます。
また最近はノーコード/ローコードツールも充実しており、プログラミングの知識がなくても業務アプリを作成できるサービスもあります。
自社にITエンジニアがいなくても使えるツールを選べば、現場主導でのDXも進めやすくなるでしょう。
段階的な導入を心がける: DX初心者の企業は、一度に大規模なシステムを入れるよりも、扱いやすいツールから導入して効果検証しながら進めるのがおすすめです。
例えば、まずは一部署・一業務でテスト導入し、使い勝手や効果を確認してから全社展開するアプローチです。
マーケティング部門なら、顧客データ管理のシステムを先に導入して運用ルールを確立した後、営業やカスタマーサポート部門ともデータ連携する、といった段階を踏むとスムーズです。
事例: 具体的な活用イメージとして、「問い合わせ対応の自動化」を考えてみましょう。
従来、問い合わせフォームから送信された内容を担当者が手作業で社内共有し顧客データベースに入力していたような場合、これをツール連携で自動化すれば大幅な効率化が図れます。
例えば「フォーム送信→データベースへ自動登録→社内チャットで通知」という一連の流れをシステムでつなぎ込めば、人手による転記作業が不要になり対応もスピードアップします。
事実、ある企業ではこの仕組みを導入した結果、請求書や納品書の発行業務にかかる時間を7割削減し、本来注力すべき顧客対応にリソースを振り向けることができるようになりました。
このように自社課題にマッチした適切なツールを選び活用することで、DXの効果を着実に得ることができます。
ステップ5:小さく始めて継続的に業務プロセスを改善する

最後のステップは、実際の運用に乗せてPDCAを回し、継続的に業務プロセスを改善していく段階です。
DXは導入して終わりではなく、社内に定着させ効果を最大化するための地道な改善活動が欠かせません。
よくある課題: システムやツールを導入したものの、使いこなせずに現場が元のやり方へ戻ってしまうケースがあります。
これは「導入が目的化」してしまい、その後のフォローやプロセス改革が不足したために起こります。
また一度に大きな変革を狙いすぎて挫折することもありがちです。
中小企業ではリソースが限られる中で急激な変化を起こすと、現場が混乱してかえって生産性が落ちるリスクもあります。
さらに、DX推進の効果がすぐに見えないと経営者の熱意が薄れプロジェクトが頓挫する恐れもあります。
解決策: スモールスタートで小さな成功体験を積み重ねながら、PDCAサイクルを回して順次改善を行うことが重要です。
まずは取り組みやすい業務から着手し、成果を検証しましょう。
例えば紙で行っていた申請処理を電子化するとか、部署内の情報共有にチャットツールを導入するといった短期間で効果が出やすいテーマから始めるのです。
そこで得られた効率化の成果(時間短縮やミス削減など)を定量的に測定し、社内で共有してください。
成功事例は社内報告や朝会などで発表し、関係者を称賛・表彰するのも良い方法です。そうすることで社員のDXへの前向きな姿勢が醸成され、次の施策への協力も得やすくなります。
次に、定期的な振り返り(レビュー)を実施します。DX推進チームで月次・四半期ごとに進捗を確認し、課題があれば原因を分析して改善策を立案しましょう。
計画(Plan)→実行(Do)→検証(Check)→改善(Act)のPDCAサイクルを回し続けることで、DX施策の精度と効果を高めていくことができます。
例えばマーケティングオートメーションを導入した場合、定期的にKPI(開封率やCVRなど)をチェックし、シナリオや施策を改善するといった流れです。
さらに組織文化の変革も視野に入れてください。
DXを軌道に乗せるには、社員一人ひとりがデジタル技術を活用した新しい働き方に順応し、自発的に改善提案できる文化を育む必要があります。
経営者や管理職は率先してデジタルツールを活用する姿勢を示し(率先垂範)、現場のメンバーは失敗を恐れずチャレンジする風土を作りましょう。このようなオープンな雰囲気づくりもDX成功の重要なファクターです。
事例: 業務効率化を目的にDXを進めたある企業では、まず在庫管理をスプレッドシートからクラウド在庫管理システムに移行しました。
在庫情報がリアルタイムで共有できるようになり、在庫過不足の削減という成果を達成しています。
その成功を社内で共有したところ他部門からもDX施策の提案が出るようになり、次に営業プロセスの見直し(顧客情報の一元管理)が始動しました。
このように小さな成功→水平展開を繰り返すことで、最終的には業務全体の大きな変革につなげていくことができます。
DXは一朝一夕に完了するものではありませんが、継続的な取り組みによって着実に成果を積み上げていくことが可能です。ぜひPDCAを回しながら、貴社のビジネスモデル変革に向けてDXを推進していきましょう。
まとめ:DXの第一歩を踏み出し継続することが成功への近道
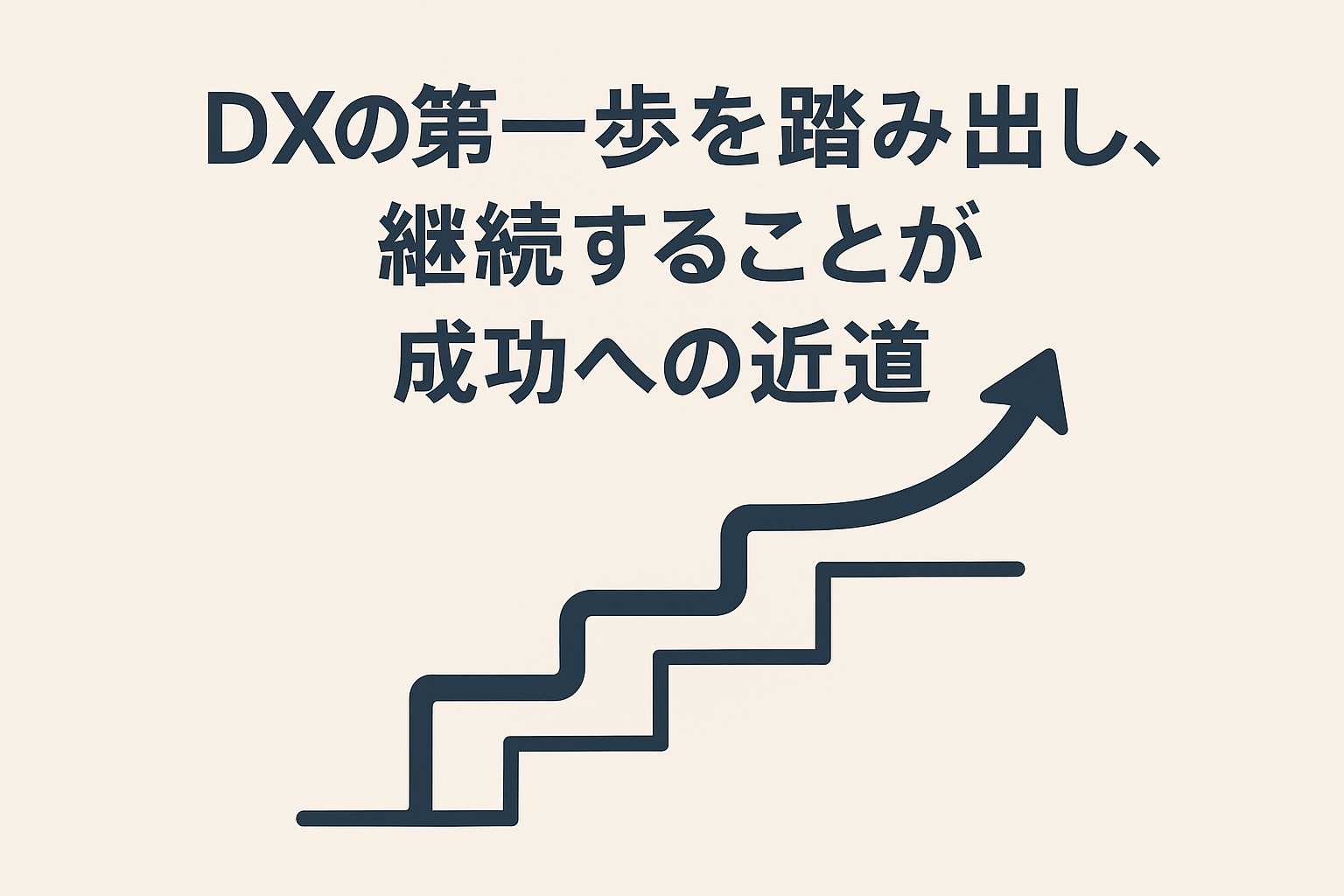
以上、DX推進に悩む中小企業の担当者向けに、成功に導く5つのステップを課題と解決策とともにご紹介しました。
自社の課題を見極め目的を定めることから始まり、人材・リソースの確保、適切なツール導入、小さな成功の積み重ねまで、一連の流れを着実に踏めば必ず道は開けます。
DXは部分的な効率化にとどまらず、ゆくゆくは新たな価値創出やビジネスモデルの転換にもつながる中長期の挑戦です。まずはできるところから着実に実行し、社内にDXの文化を根付かせることが「自社でのDX成功」への近道と言えるでしょう。
とはいえ、自社だけでDXを進めるのは難しい…と感じる方へ。
マーケティング業務のDX推進でお悩みの場合は、専門家の力を借りることも一つの手です。
例えば弊社が提供しているオートラクボでは、中小企業向けにマーケティング業務DX支援サービスを提供しています。
既存のクラウドツールやシステム同士を連携させて「人が行わなくてよい作業」を自動化し、業務効率化を実現することが可能です。
自社に開発部隊がなくても、今お使いのツールをつなぐだけで低コストでの自動化環境構築を代行してもらえるため、従来の大掛かりなシステム導入よりリスクと費用を抑えてDXを進められます。実際に7,000種以上のサービス連携実績を持つなど豊富なノウハウがあり、フォーム問い合わせ対応の自動化やデータ集計の省力化など、マーケティング現場の具体的な課題に即したソリューションを提案してくれます。
DXの道のりで「専門的なサポートが欲しい」と感じたら、ぜひオートラクボに相談してみてください。
プロの支援を得て自社のDXを加速させ、競争力強化につなげていきましょう。
お問い合わせは下記からお気軽にどうぞ。
あなたの会社のDX成功への一歩を、私たちがお手伝いします。